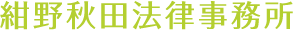私は、司法試験に合格し、司法修習生になっても、将来何になるかほとんど頭になく、日々を過ごしていました。そんなある日、ある福祉施設で、休日を利用して、重度身体障害児のボランテァをやっていたことがありました。この時、ボランテァ仲間と遭遇した、ある少女の話があったのです。
彼女は、ある小さな町工場で、針仕事を主な内容として働いていたのですが、ある時、一心に作業中の彼女の肩をたたいて社長が「○○ちゃん、明日から来なくていいよ」と言ったのです。彼女は、その意味を理解しました。要するに人減らしです。不況の影響が一番弱いところに来たのでした。彼女は、自分が一番好きで、一番得意で、みんなからもほめてもらえる仕事を失ったことがとても悲しく、大粒の涙がほほを流れました。それでも、涙をぬぐうこともせず、静かに泣きながら、作業の手を休めず、いつもと同じように仕事を続け、いつもと同じように仕事を終わり、いつも同じように家に帰りました。しかし、たった一つ違っていたのは、いつも職場のみんなが「さようなら、○○ちゃん、また明日ね」と言うのですが、この時は「さようなら」だけでした。彼女はよく理解していました。誰も助けてくれないことを。今まで、小さい頃から、いじめられても、疎まれたりしても、じっと我慢して、一所懸命に自分のできることをやってきました。しかし、小さな町工場に誰も教えてくれる人もいませんでした。誰も次は自分ではないかと不安でいっぱいで助けようともされないのです。
私は、ボランテァ仲間から詰問された。
「おまえは、弁護士だろう、何とかできないのか」
・・・いや、ぼ、僕はまだ、見習いの司法修習生で・・
「だって、おかしいだろう」
・・・だから、民法の規定では雇用契約の解除は正当な事由がないと認められないと思いますが・・・
「どうするんだ。何だ、分からないのか、さてはお前は、ニセ弁護士だな」
私は、この時、確信しました。そうだ、この町工場のこの少女の事件に立ち向かえるのは弁護士しかいないのだ。こうして、私は、はっきりと、弁護士になることを決意しました。
私は、法律相談を担当する度に、社会の隅々まで法の光が届くように、一隅を照らす弁護士になりたいといつも思うのです。あの大粒の涙を流しながらも、手を休めることもなく働き、静かにひとりで帰って行った少女を思い出しながら。
了